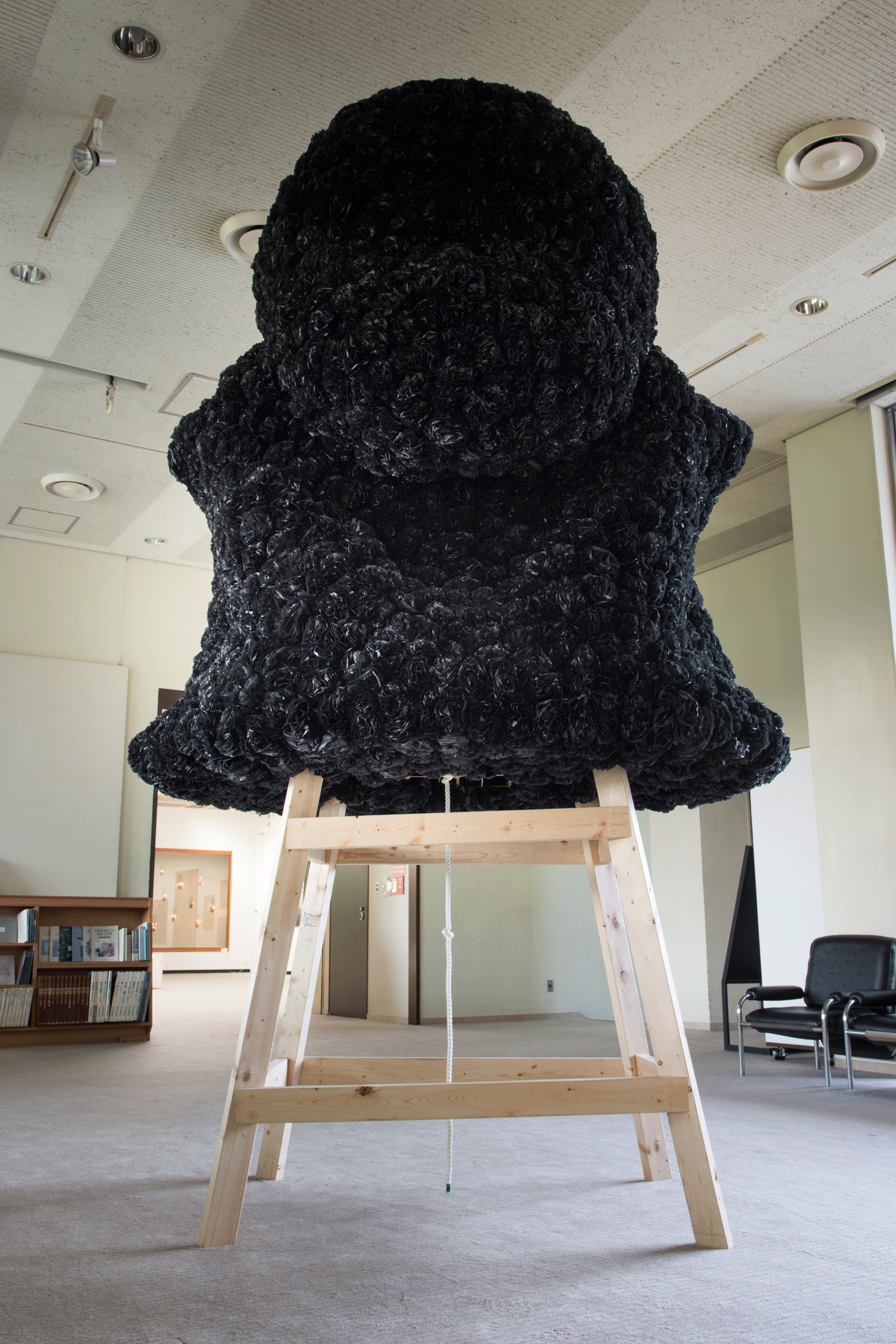|  |  |
|---|---|---|
 |  |  |

わたしの個人的な主観ではあるが、真部知胤の作品は無理矢理アートの文脈にのせてみて、その存在意義をおもしろがれるわけでもなく、表面的な技巧をおもしろがれるわけでもない。
ましてや個人的な諸問題をポエティックにイメージ化するような表現は見当たらない。
過去の作品には、部屋に蓄積していく埃を集めてつくられた土偶に似たものや、広告チラシを細く丸め籐を編むようにつくられた縄文土器などがある。
不思議なことだが、このような単純な行為の繰り返しによってつくられた真部の作品を見ていると、なぜ土偶や縄文土器なのか、なぜ埃や広告チラシなのか、その問いかけ自体が不毛であるような、そんな気さえしてくる。
真部の作品は、何かしからの意味づけを遠ざける性質をもっているのかもしれない。
それは、家の縁側に座りどこを見るわけでもなく目の前にある庭をただ眺めているだけで充実感(美)を味わえるような、見ているものに意味づけの必要性をもたない、きっとそういったものである。
仮にだが、真部の作品が「意味づけの必要性をもたないもの」であれば、それは「無為」な時間によって生成されたものであるように思える。
「無為」な時間とは、合目的な「~のため」といった言葉を否定していくことである。
それは、生きていくうえで身につけていく複数の言語が、自らの身勝手な都合に合わせて限定(固定化)されることなく、その場の状況によって流動的に切り替わっていくさまである。
端的に言い換えるならば、先入観や偏見、等価以上の見返りを求める意識を回避していくことができる軽い心持ちと言ってもよい。
そのような「無為」な時間の流れによって生成されつくられたものは、「こうあるべきである」といったつくり手の自我の押し売り的な意味づけは、さほど魅力的なものとして意識のうえに立ち上がることはない。
そのようにひとつの意味に回収されない流動的な意識のありかたは、間口が広く受動的な性質をもっていなければ成り立たない気がする。
厳密に言えば、能動的な意識は受動的な意識に対立するものではなく、多くの言語を受動していく意識の流れのなかのひとつの出来事にすぎないということである。
ここでひとつの興味がわいてくる。
このような一見捉えどころがない意識の持ちかたでつくられた作品が、はたして現在のアート事情のなかでどのような存在感を示すのだろうか。
わたしは、ひとりでも多くの人にその目撃者になってもらいたいと願うばかりだ。
(美術家、ゲルオルタナ代表 栗原一成)
真部 知胤 Tomotsugu MANABE
1981年 香川県生まれ
2009年 多摩美術大学大学院修了
展示
2013年 〈わたしたちのそういう時間〉 JIKKA(東京)
2013年 〈的のその先〉 アキバタマビ21(東京)
2012年 〈アートプログラム青梅『存在を超えて』〉 青梅市立美術館(東京)
2012年 〈SLASH/07 できるだけ遠くをみろ〉 nap gallery(東京)
2010年 〈あらゆる場所から遠くはなれて〉 作家アトリエ(神奈川)
2009年 〈ANOTHER FUNCTION〉 筆屋コーポレーション(東京)

木目(恵比寿様、大黒様、薪、熊)
2013 発泡スチロール、絵の具
サイズ可変
シェルター(FUKUSUKE Ver.)
2013 お花紙、避難用ロープ、木
h350×w180×d170cm